
個展がプレスリリースされてすぐに、プリント購入を決めた。まだ見ていなくても確信めいたものがあった。今回の新作はやばいぞ、と。たまにそういうことが起きる。
福山えみさんの写真は、見ればすぐに福山さんのだとわかる。「そうそう、これこれ」となる。初めてでも数枚みればその特徴をつかめると思う。手前に遮蔽物があり、奥を覗くような視線。一定の温度と湿度を保ったねむいトーン。プリントを観るたびに、なにかを予感させ、胸をざわつかせる。不思議な魅力をもつ写真だ。
今回の『岸を見ていた』を初めて観たときに、「月がついてくる」や「A Trip to Europe」と比べて、なにかが決定的に違う印象を受けた。大きな変化もなく、作風はそのままなのに、ざわつきようが尋常じゃないのだ。
メインヴィジュアルになっている1枚目が特にそうだ。自動車の後部座席の窓から野花を見つめるイメージで、なんでもなさそうでいて、なにかがある。「すごさ」というよりも、「危うさ」を感じた。「福山さん、大丈夫?」って。
ただ、こうだと決めつけられない。危うさの中にも安心感がある。陽とも陰ともつかない。彼岸と此岸ととらえられなくもない。彼岸にピントが合っているので、そちら側に意識があるとは思えるけど、かといって此岸から見ているともいいきれない。実はその逆かもしれない。
ようするに、福山さんの意識が、その空間、次元の間(あわい)にいるような感覚だ。どちら側にもいるようでいて、どちら側にもいない。ギャラリーの柿島さん曰く「幽体離脱をして俯瞰してその状況をみている」と表していた。確かにその感覚に近い。
こういう写真を撮る根底にあるものはなんだろうと考えたときに、尾仲さんとのトークでヒントをもらえた。
「子どものころに、夜ひとりで眠るのが怖くて、両親の寝室にいくんだけど、眠っているところに潜り込んでいく勇気もなく、起こしてしまって今の状況が壊れてしまうのも嫌で、両親が気づくまでそばで座って待っていることがよくあった」と言っていたのだ。
ことが起きる前、ことを起こす前の、なにかを予感させる距離感を常に維持している感じ。望んでいることはあるのに、そこには自ら踏み込まない。その状況はが楽しいわけでもなく、かといって望みをあきらめてもいない。間(あわい)の妙がこの福山作品の根底にある気がする。
作品の発表はマイペースで、どちらかといえば寡作といえる写真家だろう。でも福山さんにとって展示と展示の間のインターミッションこそが作品づくりに欠くことのできない時間なのだとしたら、福山さんにとってごく自然なペースなのかもしれない。
寄稿している「街道マガジン」でもふれているが、福山さんは体調を崩して入院した時期があった。期を同じくして、愛用のマキナも壊れ、仲良く入院となる。今回の作品は、復帰してからの一年くらいの撮り下ろしだという。作品を見た後に、改めてステートメントを読み返すと、ここ一年の精神的、身体的なもどかしい状態を感じ取ることができる。
本来持っている間(あわい)の意識に、不調で前に進めぬもどかしさが加わった。また人生のある転機も迎えている。福山さんのインターミッションは、確実に今作にも影響を与え、その本質的な要素が濃縮され深化している。もはや輪廻している感もある。さらにすごみを増しているのに、当の本人はあいかわらずのテンションなのが、またすごいと思ってしまう。
展示でも写真集も最後の配されている木の影のイメージも好きなカットだ。とても初々しくて、撮る喜びに満ちあふれている。これからの福山さんの活動を予感させるものだった。少し長めのインターミッションは、作品を確実に深化させた。さらなる深みを見せてくれるのか、それとも新たな変化を示すのか。これからどう発展するのか予想はつかないが、あらためて撮る喜びを感じている福山さんの作品が今まで以上にたのしみでしかたがない。
以下、改めてプレスリリースの引用です。
私と向こう岸の間には、大きな小さなたくさんの水のうねり。
流れは速くないが、とどまることなくうねり続け、なかなか渡れそうもない。
私の立っているところは、やはりこちら側の岸なのだろうか。
いや、水上の流れに身を任せて漂っている小舟かもしれない。
ゆらゆらと不安定なその足元になんとかこらえて立ちながら、
うねりの向こう側にある岸を見ていた。
ただ静かにそこにある岸。
そんな一年だった。
-福山えみ-


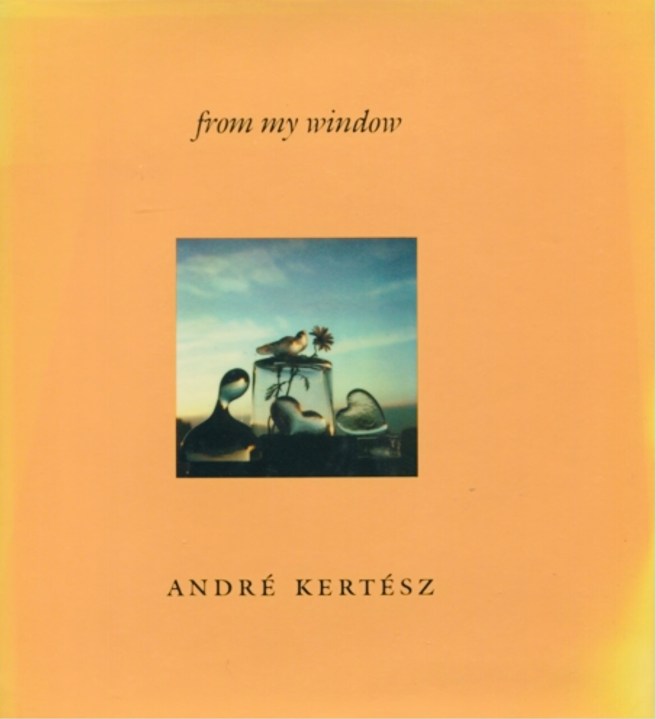
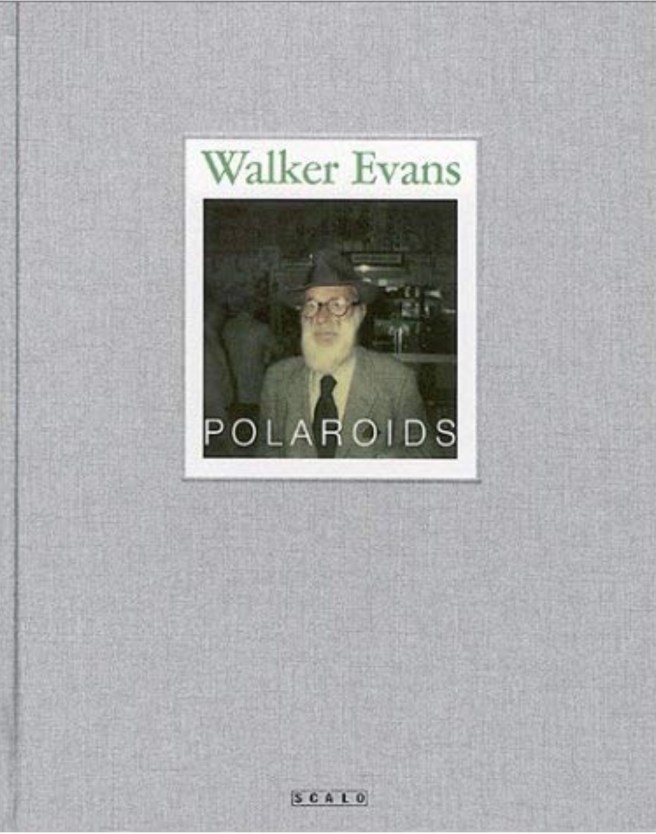
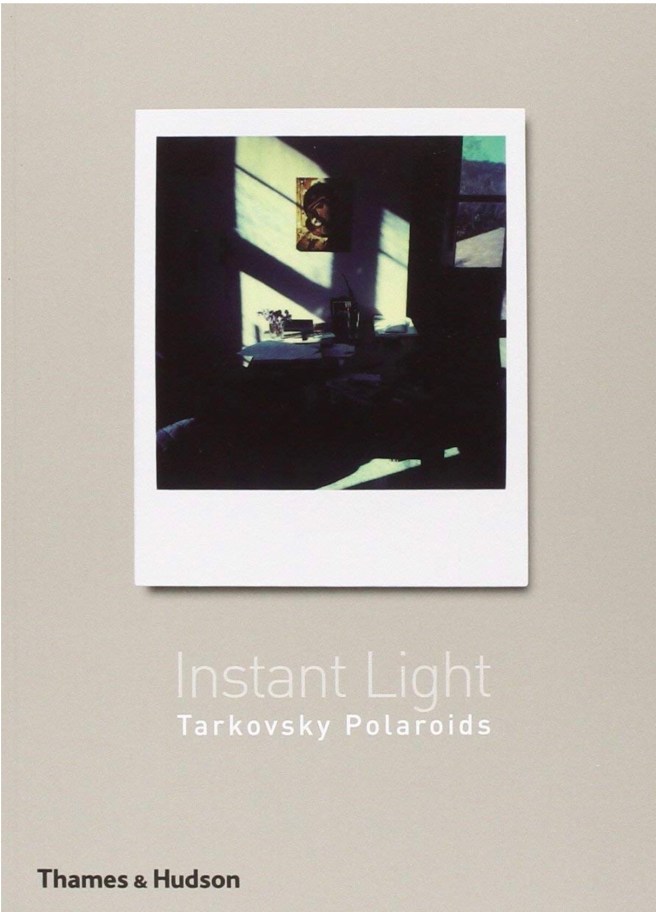


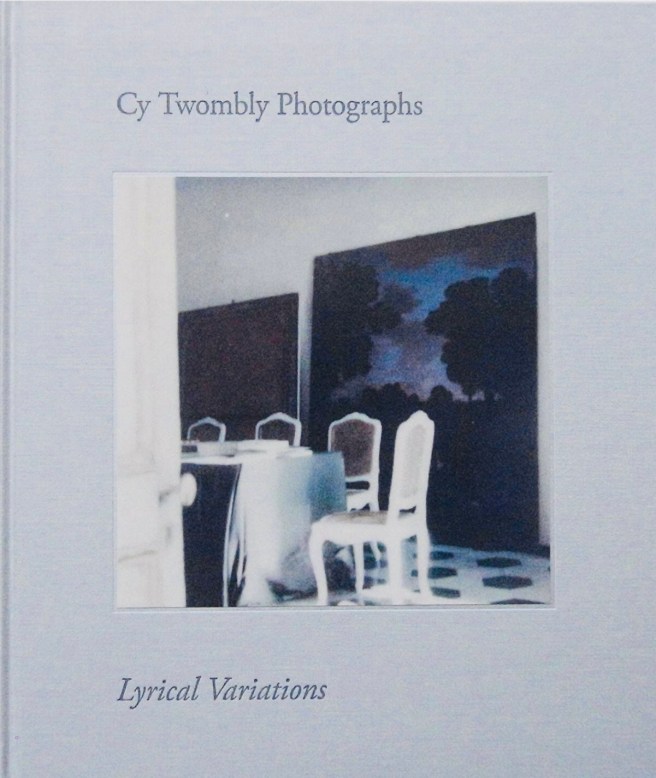




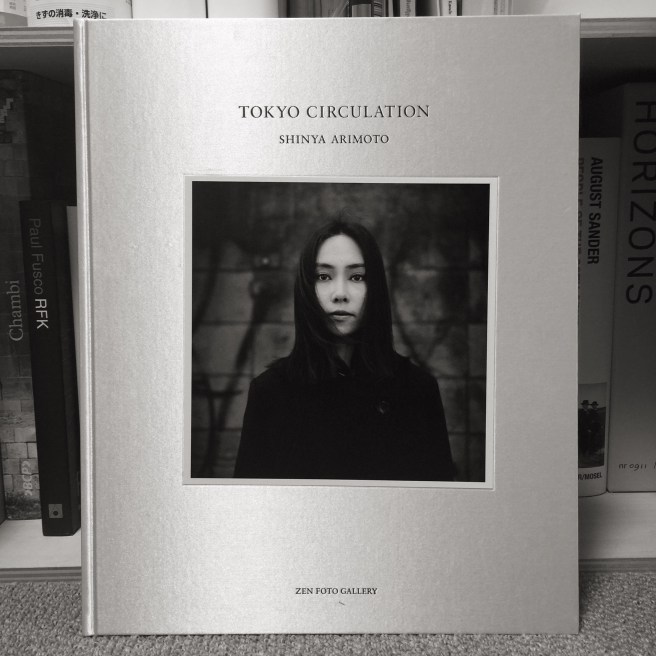

















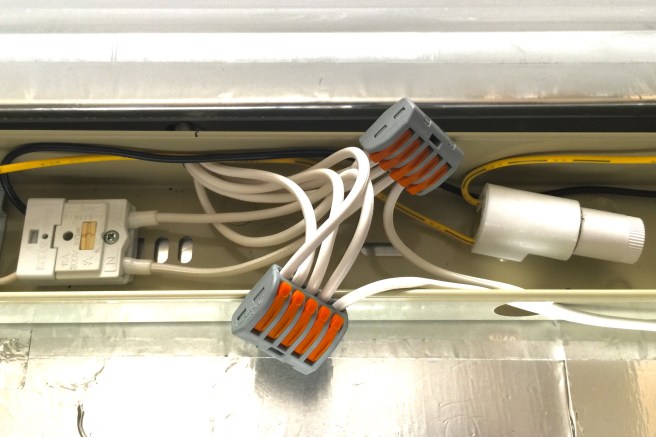


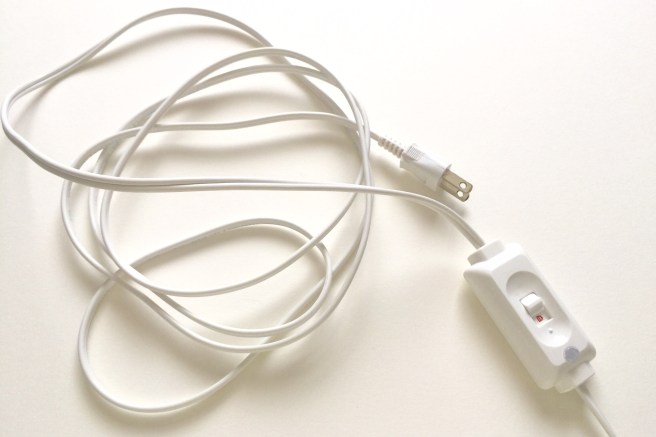
コメントを投稿するにはログインしてください。